2025年は税制にいくつか大きな変更があり、これまで通りのやり方では思わぬ損をしてしまう可能性があります。特に「青色申告特別控除(65万円)」を確実に受けるには、正しい知識と事前の準備が欠かせません。
本記事では、一人親方が陥りがちな申告ミスをわかりやすく解説し、2025年の最新税制にどう対応すべきかを詳しくご紹介しています。
専門的な視点をもとに、申告業務を効率化しながら、手取りを最大化するための具体的な節税テクニックも掲載。
四国中国エリアで活動する一人親方の方々に向けて、スムーズに確定申告を済ませるための実践的な情報をまとめました。
余計な税負担を防ぎ、しっかりと事業を守るために今から準備を始めましょう。
正しい申告が、あなたのビジネスの安定と未来を支えます。
建設業界で日々現場を支える一人親方の皆さんにとって、確定申告の時期は大きなプレッシャーを感じるタイミングではないでしょうか。特に毎年のように制度が変わる中、最新情報を把握していないと、「思わぬ追徴課税」や「控除の取りこぼし」といったリスクに直面してしまいます。
そこで今回は、一人親方が確定申告で陥りやすい5つのミスと、その具体的な対処法について詳しく解説します。
① 経費の計上漏れ
建設業では日々の出費が多く、経費の種類も多岐にわたります。中でも見落としがちなのが、自家用車を業務に使用している場合の費用按分です。
たとえば、ガソリン代や車検費用、保険料などは、業務に使った分を按分して経費計上できます。
対策としては、作業日報に走行記録を残す・給油のたびにメモを取るなどして、業務使用割合を客観的に示せる証拠を整えておくことが重要です。
② 青色申告特別控除の要件を満たしていない
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の条件をすべてクリアする必要があります:
-
複式簿記での記帳
-
損益計算書・貸借対照表の作成
-
電子帳簿保存
-
e-Taxでの電子申告
このように要件が厳格化された今、クラウド会計ソフトの活用はもはや必須です。「freee」や「マネーフォワード クラウド確定申告」などは建設業向けの仕訳にも対応しており、簿記の知識が浅い方でも安心して導入できます。
③ 源泉徴収の処理ミス
元請業者から報酬を受け取る際に源泉徴収されている場合、確定申告で精算することで還付を受けられる可能性があります。
重要なのは、源泉徴収票を必ず保管し、「確定申告書B」の該当欄に正しく記載することです。特に大手ゼネコンと取引している場合は、源泉徴収が発生していることが多いため、確認を怠らないようにしましょう。
④ 事業主貸・事業主借の混同
個人の支出と事業の支出が混在すると、帳簿の管理が煩雑になるだけでなく、税務調査時に不自然な動きとして指摘される可能性があります。
事業用と私用の銀行口座・クレジットカードは必ず分けて管理し、資金の動きがひと目でわかるようにすることが基本です。また、「事業主貸」「事業主借」として帳簿に正確に記録する習慣も重要です。
⑤ 消費税の課税事業者判定
年間の売上が1,000万円を超えた場合、原則として翌々年から消費税の課税事業者となります。ここで見落としがあると、消費税の申告漏れや罰則につながるおそれがあります。
ただし、課税事業者になることで仕入れや資材購入時の消費税分を控除できるメリットもあるため、一概に不利とは限りません。制度が複雑なため、必要に応じて専門家に相談するのが安心です。
たとえば「辻・本郷税理士法人」などでは、一人親方向けに無料の個別相談会を開催しており、こうした機会を活用することで、正確な判断ができるでしょう。
確定申告の期限が迫ってきました。今年は建設業や運送業などで活躍する一人親方の方々にとって、特に注意すべき税制改正がいくつかあります。適切に対応しないと、余計な税負担や控除漏れにつながる可能性も。この記事では、2025年における主な変更点と節税のポイントをわかりやすく整理しました。
■ インボイス制度の本格スタートに注意!
2024年から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が本格的にスタートしました。これにより、仕入税額控除を受けるためには、取引先から受け取る請求書が「インボイス(登録番号付き)」であることが必須です。
また、あなた自身が課税事業者であれば、自分が発行する請求書にも「登録番号」「税率ごとの消費税額」などの記載が必要となります。登録がまだの方は、今すぐ国税庁のサイトで申請状況を確認しましょう。
■ 青色申告特別控除の条件が厳格化
青色申告特別控除の最大額である65万円を受けるには、「電子帳簿保存」+「電子申告」の両方が必要です。これまで紙で提出していた方も、65万円控除を継続するには、e-Taxを使った申告が必須となります。
クラウド会計ソフト(例:freee、MFクラウドなど)を活用すれば、帳簿作成から電子申告までを効率化できます。忙しい一人親方にこそ、早めの導入がおすすめです。
■ 自宅兼事務所の経費按分に要注意
自宅を事務所として使っている場合、水道光熱費や家賃の一部を経費に計上できますが、最近は按分の根拠資料を税務署が厳しくチェックするようになっています。
例えば、仕事に使っている部屋の広さ、作業時間、電気使用量の割合などを具体的な数値で示せるよう、事前に資料を整えておくことが重要です。
■ 節税の強い味方「小規模企業共済」「iDeCo」
一人親方にとって効果的な節税策として、以下の2つは見逃せません:
-
小規模企業共済:掛金全額が所得控除となり、退職金代わりの積立にも。
-
iDeCo(個人型確定拠出年金):老後資金の準備と節税が同時にできる。
どちらも国が支援している制度なので、節税しながら将来に備えることが可能です。まだ加入していない方は、この機会に検討してみてください。
■ 設備投資にも減税メリットが
2024年も、事業用の設備投資に対する「即時償却」や「税額控除」などの優遇措置は継続中です。新たな工具や機械、車両などを導入した場合は、これらの制度を活用することで税負担を軽減できます。
■ 社会保険料の控除も忘れずに
国民健康保険料や国民年金保険料は、全額が所得控除の対象になります。また、事業に関係する保険料や社会保険料については、必要経費としての計上も可能です。領収書や納付証明書はしっかり保管しておきましょう。
一人親方として事業を営んでいる方にとって、青色申告特別控除の65万円は、税金を大きく節約できる非常に重要な制度です。ところが、正しく対応しなければ、控除額が10万円にとどまってしまうことも。
ここでは、65万円の控除を確実に受けるためのポイントを、実務に沿ってわかりやすく解説します。
① まずは「青色申告承認申請書」を期限内に提出!
控除を受けるには、まず税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
-
新規開業の場合:開業から2ヶ月以内
-
既に開業済みの方:対象年の3月15日まで
この期限を過ぎてしまうと、翌年からしか65万円控除が使えなくなるので、忘れずに提出しましょう。
② 「電子帳簿保存」と「e-Tax申告」が65万円控除の必須
2020年以降、65万円控除を受けるには以下の2つが絶対条件です。
-
電子帳簿保存
-
e-Tax(電子申告)での提出
この条件をクリアするには、クラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワードなど)の活用が非常に便利。
取引データの自動取得や仕訳の提案など、帳簿作成から申告までスムーズに対応できます。
③ 複式簿記での記帳が必要(単式簿記では55万円まで)
青色申告控除の額は、記帳方式によって変わります。
-
単式簿記の場合:最大55万円
-
複式簿記を満たし、電子申告も行った場合:最大65万円
複式簿記は一見難しく感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを使えば自動で複式簿記の形式に変換してくれますので、簿記の専門知識がなくても安心です。
④ 損益計算書・貸借対照表の作成と提出も忘れずに
青色申告で65万円控除を受けるためには、以下の書類を確定申告書と一緒に提出する必要があります。
-
損益計算書(収益と費用の状況)
-
貸借対照表(資産と負債のバランス)
これも会計ソフトで自動作成が可能です。数クリックで完了するので、難しく考える必要はありません。
⑤ 事業用と個人用の口座を分けておくのが実務上のコツ
法的な必須条件ではありませんが、事業用の銀行口座と個人用口座を分けることは、経費管理や税務調査のリスク軽減に非常に効果的です。
帳簿管理もシンプルになり、経費の証明もしやすくなります。
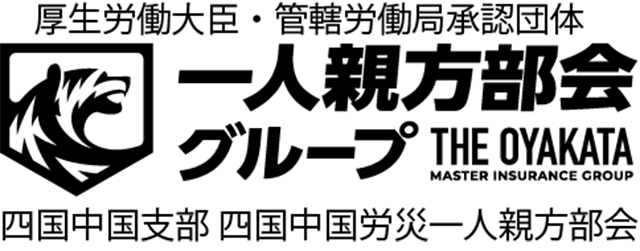



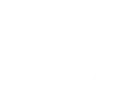

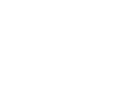











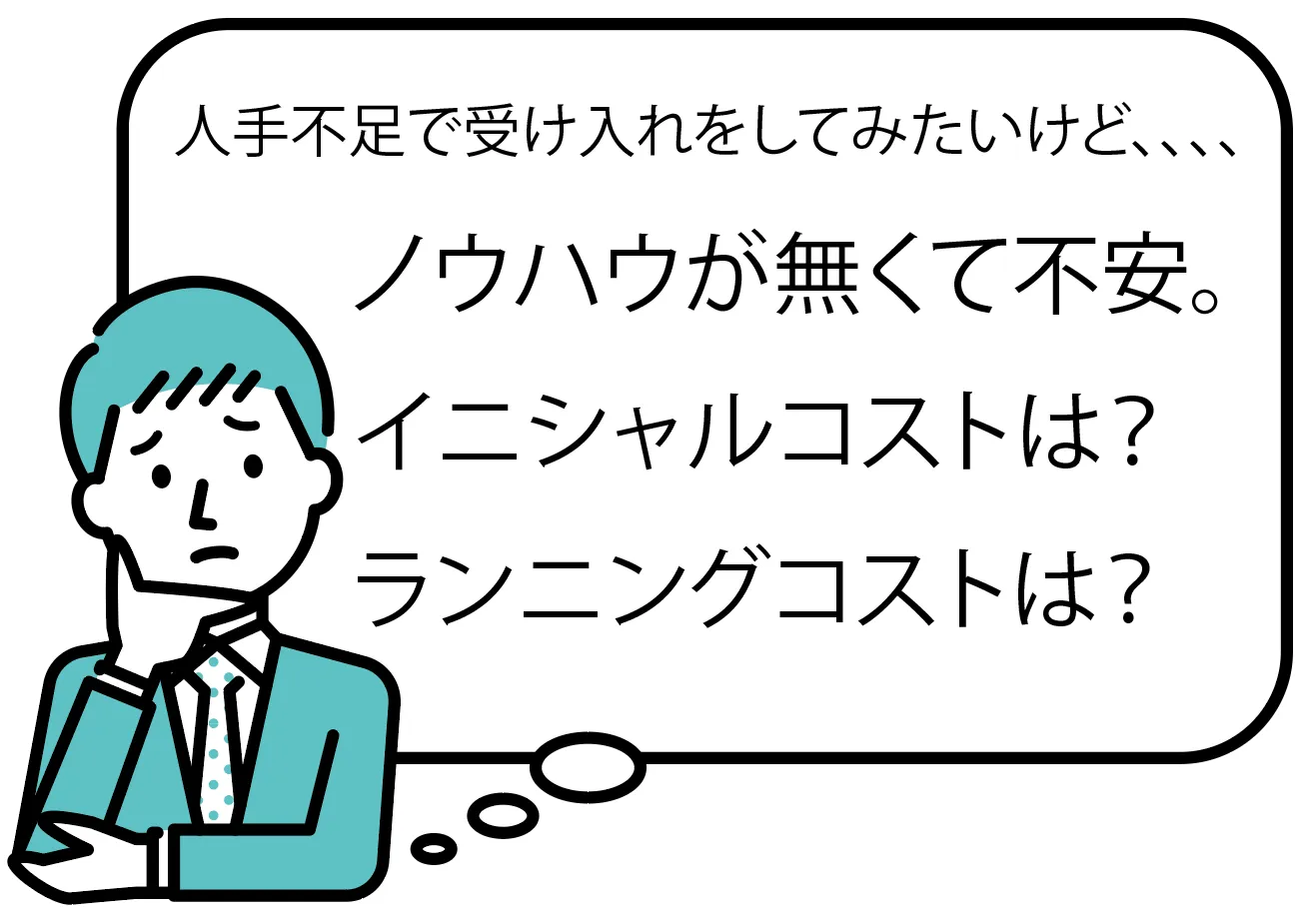

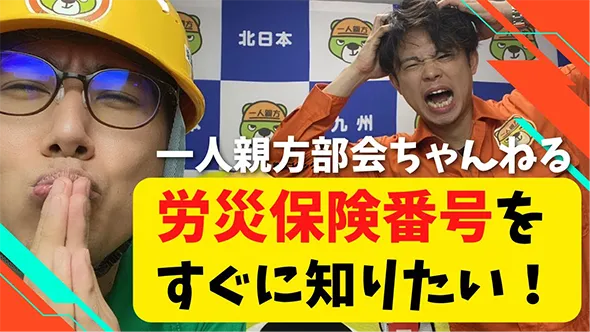








 お申し込み
お申し込み 今すぐお電話
今すぐお電話